近年、「やる気のある無能は危険」という言葉がネット界隈にて浮上してきている。一般的に、やる気のある人は価値があると認識されている。しかし、その人が「無能」とされる場合、組織にとって危険と言う様な風潮が存在する。
本記事は、やる気が溢れているが、まだ能力や経験が十分でない若手社員と、彼らと日々共に働く組織や企業に向けたメッセージとして書かれている。やる気のある若手が組織にどのような価値をもたらすのか、そして組織として彼らをどのようにサポートすべきかを考察する。
ハンス・フォン・ゼークト氏の組織論
近年、業界の中に「やる気のある無能」はリスクだという風潮が浮上してきている。この考えのルーツは、かつてドイツの軍人、ハンス・フォン・ゼークト氏によって示された組織論に遡ると言われている。彼は以下のように語っている。
「有能な怠け者は司令官に、有能な働き者は参謀にせよ。無能な怠け者は、連絡将校か下級兵士にすべし。無能な働き者は、すぐに銃殺刑に処せ。」
過激な表現ではあるが、やる気のある無能がトラブルの元になるとの指摘は一理あると考えられる。
このゼークト氏の考えが元となり、現代の多くの組織で「やる気のある無能」を避ける傾向が生まれているかどうかはわからないが、ネット上でやる気のある無能を悪だという記事を結構見かける。
だが私はこの理論が過大解釈され、世に偏見をもたらす風潮を生み出しているのではないかと考えている。
ツッコミどころ
ゼークト氏の組織論は、特に軍隊という特異な組織でのものである。軍という組織では、一つのミスが戦局を大きく左右する可能性が常に存在する。このような状況下では、統率力や隊員間の協調性が極めて重要となる。したがって、能力に欠けるが行動力だけが先行するような人物は、予測困難な行動を取りがちで、それが命取りとなる可能性が高まる。そうした背景から、ゼークト氏はやる気のある無能を危険とみなすという強い立場を取ったのだろう。
さらに、軍隊は常に戦場を意識している組織であり、即時に戦力として活躍できる人材が求められる。戦争という状況では、敗北は国家全体にとっての重大な危機をもたらす。このため、部下の長期的な成長を待つ余裕は存在しない。この理由から、ゼークト氏はやる気のある無能の人材を、即戦力として活用することのリスクを強調し、厳しい対応を提案したのである。
ビジネスではやる気は大切
ビジネスの現場において、技術や知識はもちろん重要であるが、それだけでは十分でない。やる気という要素が組織の成長や継続的な成功を大きく左右するのである。
では、やる気のある「無能」とされる人々は、ビジネスの現場で本当に不要なのだろうか?私は異なる考えを持っている。確かに、技術や知識がまだ未熟であるかもしれないが、その熱意や情熱は組織にとって大きな資産であると考えている。
やる気のある人は、その熱意だけで周りの雰囲気を明るくし、チームの活性化に貢献する。彼らは与えられた仕事に対するアプローチが異なり、単にタスクをこなすだけでなく、それをどうより効率的、または創造的に遂行するかを常に考える。その結果、新しいアイデアや提案が生まれることが多い。その全てのアイデアが即座に役立つわけではないが、そのような取り組み自体が組織に刺激と活気をもたらす。
逆に、やる気が欠けている組織は停滞しやすい。そこでは、仕事の最低要求を満たすことが最優先となり、新しいことに挑戦する気風や文化は生まれにくい。このような環境では、真のポテンシャルを持つ人材はその能力を発揮することなく、最終的には組織を去ってしまうリスクが高まる。
結論として、やる気は組織の持続的な成長やイノベーションを生み出す上で不可欠な要素である。そして、それを持っている人々を大切にし、彼らの熱意や情熱を最大限に活かすことが、組織の成功への道である。
無能は改善できる
無能と一言で言えば、組織にとっては生産性の低い存在かもしれない。通常の人よりも多くの作業時間がかかり失敗も多い。確かに任せて安心できる有能な人材がいればそれは理想的だ。
とはいえ、永遠に無能である人などいない。人間は常に成長し続ける生き物だ。無能とされる人に仕事を任せることは短期的な投資のようなものと捉えれば良いだろう。彼らの成長をサポートし、組織の一員としての価値を引き出すことができれば、長期的には大きなリターンをもたらすだろう。
さらに、組織としても、無能とされる人々との接点は貴重な学びの場となる。彼らがどのような作業でつまづくのか、その原因は何かを深く考察することで、組織全体の生産性や教育体制を向上させるヒントを得ることができる。
もちろん、ここで述べたような考え方やアプローチが全ての組織や状況でうまくいくわけではない。実際には、無能とされる人をサポートするコストや時間、リソースの制約など、多くの現実的な問題が存在する。また、無能とされる人全てが、サポートや教育を受けてもあまり成長しない場合もある。このような現実的な困難や課題を無視することはできない。
しかし、それでも、組織として成長や変革を求めるならば、これらの課題に直面し、それを乗り越える努力が必要だ。それは簡単な道ではないかもしれないが、長期的な成功や組織の持続的な発展を目指す上で、避けて通れない課題となるだろう。
無能よりも問題なのはリスクヘッジできない組織
無能は組織にとって大きなリスクになるのだろうか?無能が引き起こす失敗というのもある程度予測できる物である。従業員の失敗が大きな問題に発展する場合、その背後には上司の不備や監督の欠如があることが多い。もちろん、個人のミスはその人に責任があるが、組織としての問題や事態の拡大を防ぐためのリスクヘッジは上司やマネジメントの役割である。そのため、大きな問題が発生した際には、その原因や背景を探ることで、上司の責任の比重が高いことが明らかになることがあると思う。
組織における成功の鍵は、個別のミスや失敗を許容し、それを上手く処理することである。プログラミングで例えると、質の良いソフトウェアは、外部との通信エラーが発生した場合でもソフトウェアが停止するような設計とはなっていない。エラーが発生した際には、それを適切に捉え、処理し、システムが正常に動作し続ける構造が必要である。
この考え方は、ビジネスの現場においても同様である。個人の失敗やミスを「エラー」として捉えることは当然であるが、それよりも重要なのは、その「エラー」が組織全体に大きな影響を与えないようにする体制の構築である。組織としても個人のミスが大きな問題に発展しないようにする仕組みや体制が必要である。これは、単に失敗を許容するというよりも、失敗が大きな障害とならないように予めリスクをヘッジすることの重要性を示している。
組織にとって最大のリスクは人間性の歪んだ者
組織において最もリスクを持つ人材は、技術や知識の欠如ではなく、人間性の歪みを持つ者であると私は考える。この点に関して、多くの方が同意してくれるだろうと思う。
日々のニュースでも、企業の不祥事や汚職が頻繁に報道されている。これらの事件の背後には、人間性の欠如した個人の行動がある。例えば、最近報じられたジャニーズ事務所の問題も、加害者自体の人間性の問題はもちろん、それを見逃す周囲の人々の姿勢にも、深刻な人間性の問題が垣間見える。
これらは極端な事例ではあるが、日常の組織においても、人間性の歪んだ人々がもたらす悪影響は少なくない。例えば、陰湿なハラスメントが続けば、有能な人材が次々と組織を去ってしまう。このような負のサイクルが続くと、結果的に健全な人材が組織に留まらなくなり、その組織の生産性や創造性は大きく低下してしまう。言い換えれば、一人の人間性に問題を持つ者が、まるで癌の様に組織全体を蝕んでいくのである。
私の周りで起きた実例を紹介
私の経験から言えば、以下のような実例が人間性の歪みによる組織内での問題を示している。
以前ある企業にて、特定のアプリケーションに高度な機能(それほどでもない)を実装した社員がいた。その業績を背景に、彼は公然とSlack上で100万円のボーナスを要求を求める様な書き込みを始めた。最終的には、会社に対する不満や期待値のズレから、出社を拒否しその後懲戒解雇となった。
また、別の例として、ある社員がAsana(プロジェクト管理ツール)上で勝手にタスクを作成し、自己判断で業務を進めていた。彼の行動により、チームの業務フローが乱れ、何度も注意されたにもかかわらず、行動を改めることはなかった。
これらの事例は、技術的な能力や業務遂行能力とは異なる、人間性の歪みや価値観のズレが、組織の生産性やチームの調和を大きく阻害する要因となることを示している。
精神論や理想論を言いたい訳ではない
私がここまで綴ってきたのは、やる気の大切さと、人間性の歪みのリスクに関することである。しかし、私が伝えたいのは単なる精神論や理想論ではない。
事実、私自身はやる気があるタイプではない。やる気というものは、単なる精神論で簡単に湧き出るものではないと思っている。それゆえ、やる気に満ち溢れている人々の存在には、時折嫉妬さえ感じるぐらいだ。だからやる気があることの価値や素晴らしさを認識しているからこそ、これを伝えたいのである。
また、人間性の歪みについても、私の意図は「まともな人間であれ」と強要するものではない。一人一人が社会の一員として、そして組織の一員として守るべき最低限のルールやマナー、モラルを持つことの重要性を伝えたいだけだ。そもそも人間性というものに正解はないし、私の理想とする人間性を押し付けたいわけではない。
最後に私がここで述べたことはあくまで主観であり、偏見も含まれているかもしれない。それでも、この意見が読者の皆さんの心に何か触れるものがあれば幸いである。


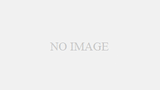
コメント